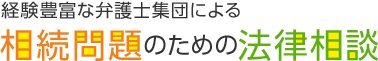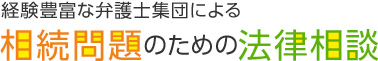生前贈与と遺留分侵害額の請求
1:相続時精算課税制度が平成15年に出来たことや孫への教育資金の贈与への非課税制度が出来たことに伴い、贈与税の負担を有る程度減らすことも出来るようになり、その結果、従前よりも生前贈与が行いやすくなっています。
もっとも、相続との関係において、生前贈与は紛争となり得ます。遺言書の有無にかかわらず、他の相続人の遺留分を侵害することもあり、遺留分侵害請求が問題となります。
2:被相続人から生前贈与された財産があり、相続人の取り分が少なくなり、その人の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額の請求(生前贈与された財産のうち、遺留分=最低限度の相続分を侵害している部分について、金銭として取り戻すこと)の対象となります。
例えば、被相続人が父親であり(母親は既に死亡)、子供が3人いる場合を考えて見ましょう。いずれも遺言書がないことを前提としています。
(事例1)
相続人の被相続人が亡くなった時点で遺産が1億円であるが、生前(5年前)、長男に2億3000万円の相当の不動産を贈与していた場合の遺留分を検討してみます。
遺産総額は3億3000万円となります(特別受益の2億3000万円を加えます。)。
各人の法定相続分は1億1000万円ずつとなります。そして、遺留分はその法定相続分である3分の1に2分の1をかけたものである6分の1相当額・5500万円となります。
そうすると、現有の相続財産である1億円を次男・三男の2人で分けても1人5000万円ずつにしかならず、次男・三男の遺留分である5500万円には到達しません(次男・三男は遺留分を500万円ずつ侵害されていることとなります。)。そこで、現有の相続財産である1億円を次男・三男が5000万円ずつ相続した上で更に、長男は次男三男に500万円ずつを払う必要があります。
(事例2)
相続人の被相続人が亡くなった時点で遺産が1億円であるが、生前(5年前)、長男に1億4000万円の相当の不動産を贈与していた場合の遺留分を検討してみます。
遺産総額は2億4000万円となります(特別受益の1億4000万円を加えます。)。1人あたりの法定相続分は8000万円となります。そして、遺留分はその法定相続分である3分の1に2分の1をかけたものである6分の1相当額・4000万円となります。
長男は、既に1人あたりの法定相続分以上をもらっているので現有財産1億円の内、いくらかでも相続することは出来ず、次男・三男が相続することとなります(5000万円ずつ)。
そして、現有の相続財産である1億円を次男・三男の2人で分けると1人5000万円になり、遺留分である4000万円を超えているため次男・三男の遺留分は侵害されていないこととなります。
(事例3)
相続人の被相続人が亡くなった時点で遺産が1億円であるが、生前(5年前)、長男に3500万円の相当の不動産を贈与していた場合の遺留分を検討してみます。
遺産総額は1億3500万円となります(特別受益の3500万円を加えます。)。1人あたりの法定相続分は4500万円となります。そして、遺留分はその法定相続分である3分の1に2分の1をかけたものである6分の1相当額・2250万円となります。
長男は、(事例2)の場合と異なり、既に1人あたりの法定相続分以上をもらっている訳ではないので現有財産1億円の内、1000万円を相続することとなり、次男・三男が4500万円ずつ相続することとなります。(事例2)の場合と同様、次男・三男の遺留分は侵害されていないこととなります。
| 現有財産 | 生前贈与 | 見なし相続財産 | 1人あたりの法定相続財産 | 1人あたりの遺留分 | 現有財産の分割方法 | 現有財産以外の交付の必要 | |
| 事例1 | 1億円 | 2億3000万円 | 3億3000円 | 1億1000万円 | 5500万円 | 0円・5000万円・5000万円 | 長男は、更に、次男へ500万円、三男へ500万円を遺留分侵害に基づき渡す必要 |
| 事例2 | 1億円 | 1億4000万円 | 2億4000万円 | 8000万円 | 4000万円 | 0円・5000万円・5000万円 | 不要・・・次男・三男は5000万円を受領することで遺留分は侵害されない *生前贈与を受けた者と受けなかった者は結果的には生前贈与を受けた者が有利となる |
| 事例3 | 1億円 | 3500万円 | 1億3500万円 | 4500万円 | 2250万円 | 1000万円・4500万円・4500万円 | 不要・・・次男・三男は5000万円を受領することで遺留分は侵害されない *生前贈与を受けた者と受けなかった者は結果的に均等となる。 |
なお、(事例2)においては、長男は生前贈与を受けていたことにより、結果的に自身の法定相続分よりも多く取得することが出来、有利となります。他方、(事例3)においては、長男は生前贈与を受けていたとしても、結局、他の相続人と同様の相続分しか相続できないこととなります。
生前贈与を受けたとしても、その額によっては、必ずしも有利になるというわけではない(事例3の場合)のです。